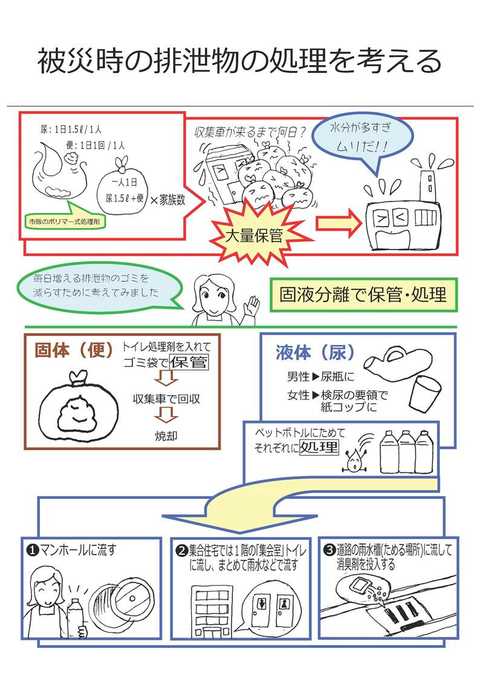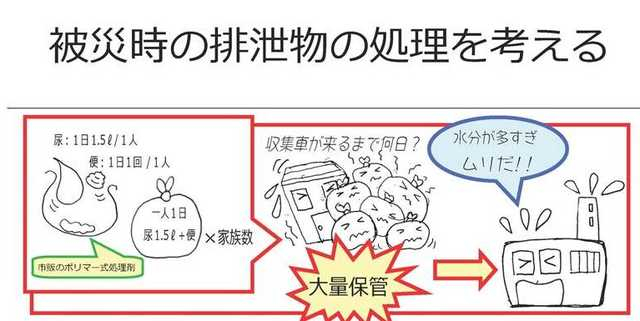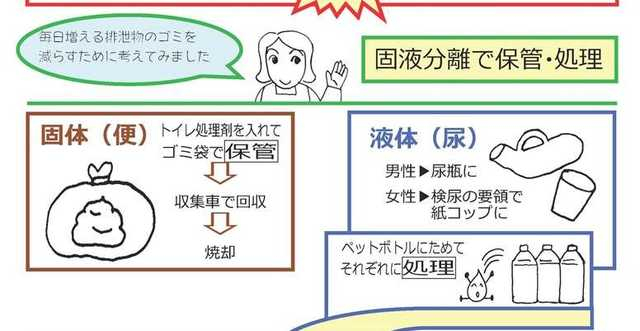第44回大田区生活展にてセミナー開催(H28年10月2日)
公開日:2019年08月08日 最終更新日:2022年11月18日
| タイトル |
被災時のトイレ対策 「第44回大田区生活展にてセミナー開催(2016年10月2日)」
|
詳細
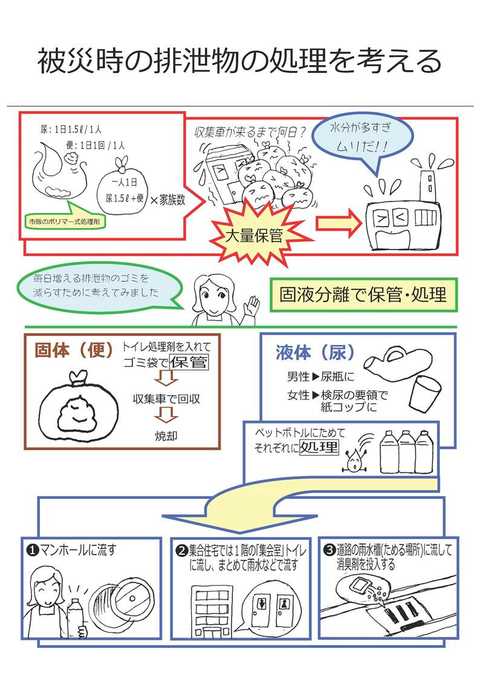 被災時のトイレ対策 ~固液分離で処理~
2016年10月12日『第44回 生活展』で、~被災時の排泄物の処理を考える~パネル紹介と、「被災時クッキング」セミナーを開催しました
大災害が発生すると、電気・ガス・水道が長期間使用できなくなる可能性があります。トイレは我慢できません!トイレが心配で飲食を控える方がいます。
「食べることは出すこと!」そんな時でも、安心して被災生活が過ごせるよう、トイレの備えと処理の仕方を心掛けておきしょう。
|
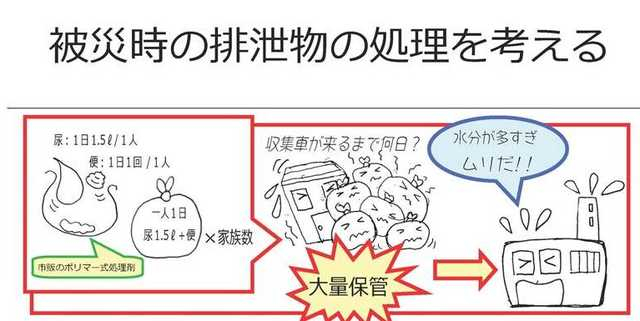 毎日増える大量の排泄物ゴミ
尿:1日一人 約1.5ℓ
便:1日1回 個人差
ポリマー式処理剤(オムツと同じ固める)で固めた排泄物は、家族の量で毎日溜まっていきます。
一方、大規模地震では道路被害がで、ゴミ収集車が長期間 回収出来ません。
さらに、清掃工場にも被害が出ている場合には、長期間処理が不可能になります。
水分を大量に含んだポリマーの汚物ゴミ(オムツと同じ)は、水分が多すぎて、焼却処理できないそうです。
|
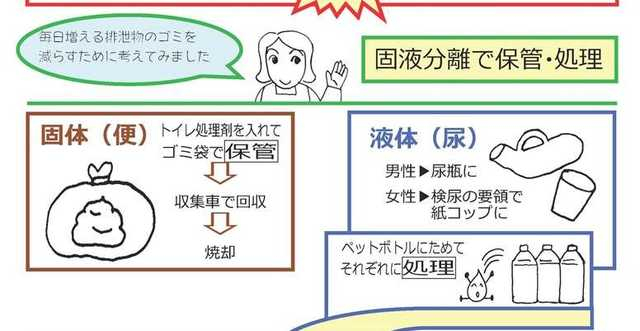 -「固液分離」で処理-
汚物をそのまま溜めると膨大な量のゴミになります。そこで、液体は側溝や排水管などに廃棄し、個体はトイレ処理剤でゴミ袋で保管しておきます。 |
 液体(尿)は排水管に流す
①マンホールに流す
溜めた尿をマンホールやマンホールトイレに流す
②集合住宅の場合
集合住宅の1階のお宅や「集会室」のトイレにまとめて流し、最後に雨水やお風呂のお湯を流しておきます。
*集合住宅の上の階の排水管が破損している場合があるので、確認できるまではトイレを流さない対応が必要です。
③側溝に流す
道路の側溝で水の溜まっているところ(排水管に直結している場所)に流し、消臭剤を投入する。
|
 トイレ対策 固液分離
「食べることは、出すこと」
被災したら、まずトイレの準備
自宅トイレは、水のタンクが壊れても便座が無事ならば、便座を上げて、便器にゴミ袋を設置して使う。
トイレの壁にタッチライトを設置しておくと、明かりが確保できて便利。
消臭剤(エチルアルコール等)も備えておく。
|
 被災時クッキングの実演
ー鍋でごはんを炊くー
停電したら炊飯器は使えません。
カセットコンロ&ボンベがあれば、鍋でごはんを炊くことが出来ます。
ご飯が炊ければ、熱々のおにぎりや、レトルトカレーをかけて、カレーライス、五目ずしの素、炊き込みご飯の素を混ぜれば、バリエーションは広がります。
ー豚汁のバリエーションー
味噌を入れれば豚汁、だしと醤油でけんちん汁、コンソメとトマトケチャップでトマトスープなど、汁物も味付けでバリエーションは広がります。
ー冷蔵庫の生食材から利用ー
冷蔵庫の生ものは、腐れば生ごみです。被災時はゴミ収集もままならないので、出来るだけ生ごみを作らないよう、調理して食べましょう。
豚の代わりにサバの水煮缶や、豆類などを活用しても美味しく出来ます。
冷蔵庫の食材が無くなったら、乾物や根菜類など常温保存できる食品を使って調理しましょう。 |
 水 ボンベの節約
ライフラインがストップした環境で、備えていた水やボンベは貴重です。被災時クッキングでは、水とボンベの節約を紹介しています。
ー水の節約ー
ペットボトルシャワーの紹介
調理器具や鍋の洗い方など
ーボンベの節約ー
加熱調理や保温を兼ねた鍋シャトルシェフや、鍋帽子による調理を紹介
ー衛生管理ー
・加熱調理が基本
・食べることは出すこと!
トイレ対策を先に準備
|