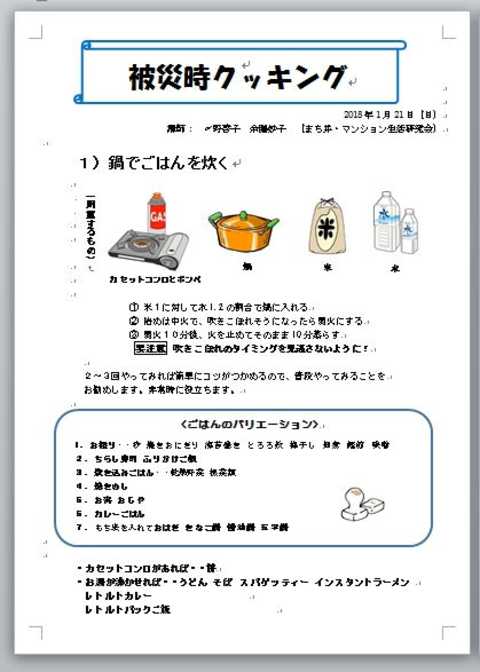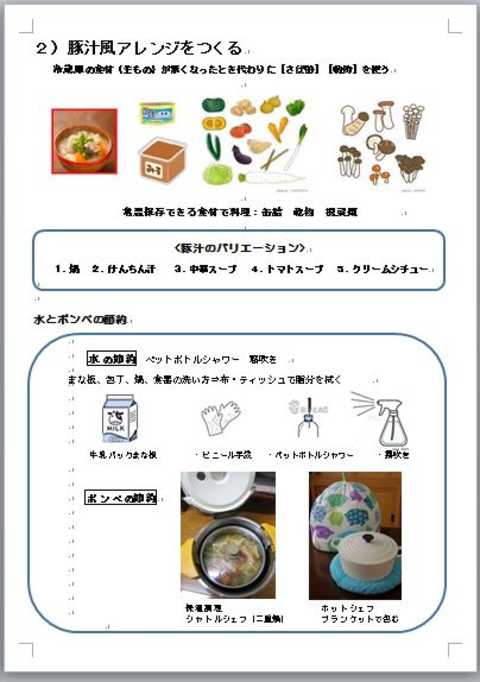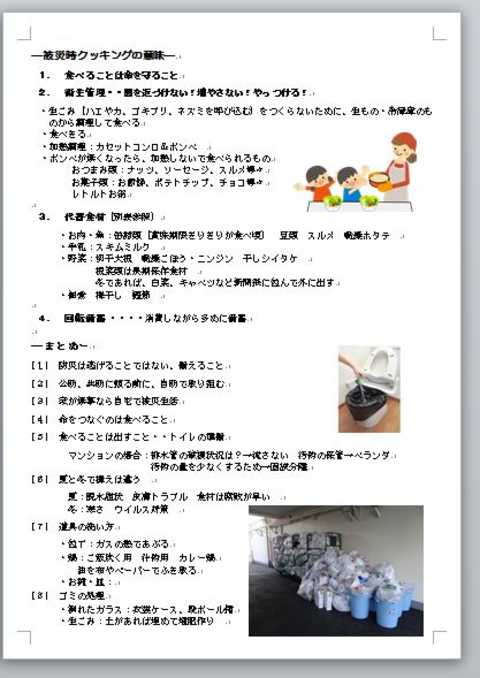女性の視点から考える防災・減災講座 「被災時クッキング」
公開日:2019年05月17日 最終更新日:2022年11月18日
| タイトル |
女性の視点から考える防災・減災講座 「被災時クッキング」 2018年1月21日
|
詳細
 主催:川崎市男女共同参画センター
女性の視点で作る川崎防災プロジェクト
日時:2018年1月21日
場所:高津市民館 料理室
講座:”被災時クッキング”
講師:〆野啓子 余膳妙子
ー被災時クッキングの考え方ー
・自宅が無事→自宅で被災生活を過ごす。
・食事で免疫力、体力を維持する。
・生きること、子どもの成長を守る。
・平常時の食事を基本に、被災時に備える。
・日ごろから回転備蓄で食材を確保する。
・トイレと衛生管理の準備をする。
|
 ①鍋でごはんを炊く
ライフラインが止まると、炊飯器は使えません。
カセット&コンロと水、お米を備蓄していれば、ライフラインが止まっても、毎日温かいご飯は食べられます。
②サバの水煮缶を使った、”豚肉の入っていない、お豆腐すいとん”
寒い冬には、食事を通して温かい汁物で体を暖めることが大切。
常温保存のきく根菜類(大根、ニンジン、ゴボウ、里芋など)や、冬なら常温保存可能なキャベツやネギなどを利用。
|
 豚汁に入れる”お豆腐すいとん”を作っているところ
ビニール袋に、お豆腐(容器にある水も利用)と小麦粉を同量入れて、子どもさんにモミモミしてもらいました。 |
 ①鍋で炊いたご飯
②サバの水煮缶を利用した”豚肉の入っていないお豆腐すいとん”の出来上がり |
 試食タイム
ー感想ー
親子で参加「子どもも興味を持って聞いていた。美味しい美味しいと言って食べました。」
男性の方から、「今までで一番参考になる講座だった。良かった」
・お豆腐すいとんが美味しい
普段のお料理にも利用したい。
・サバの水煮缶でダシの味がでているのに、おどろいた。
・鍋でごはんが炊けることが分かって良かった。
|
 乾物や缶詰、家庭菜園で収穫したネギなどで作った事例を紹介
|
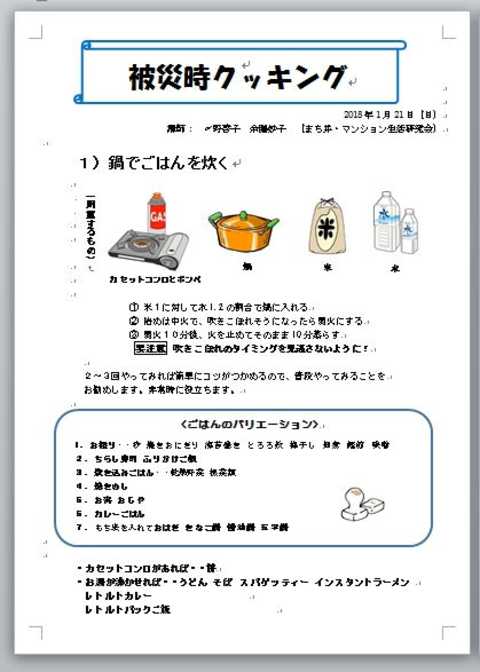 1)鍋でごはんを炊く
鍋でご飯が炊ければ、バリエーションでメニューが広がります。
ご飯メニュー
・🍙 のり 梅干し 鮭 鰹節 佃煮 ふりかけ等
・寿しの素を混ぜて、寿しご飯
・炊き込みご飯
・お粥
・カレーライス
・チャーハン |
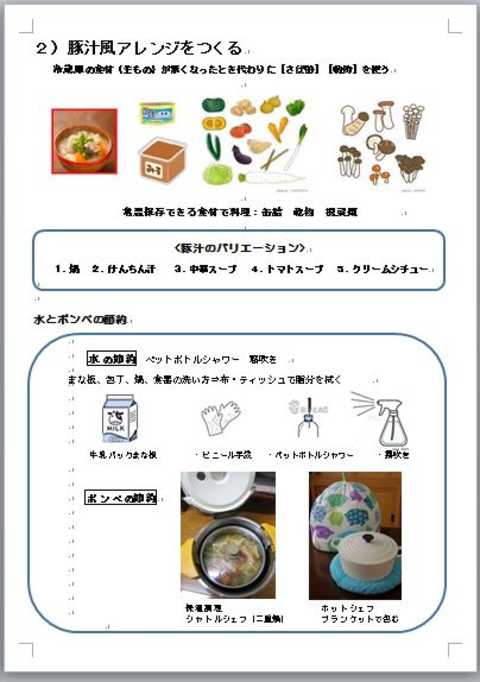 2)汁物のアレンジ
汁物は具材や調味料を変えれば、洋食にも中華にも変化します。
加熱調理や保温効果のある鍋帽子やシャトルシェフ(二重鍋)を活用して、ボンベの節約。
|
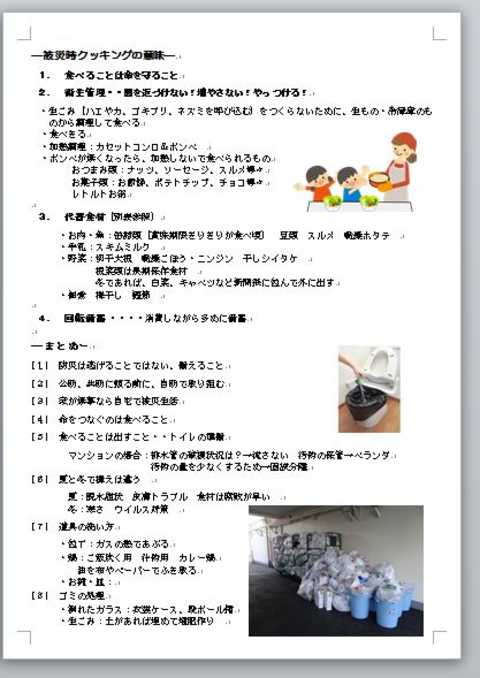 ー衛生管理ー
〇注意点
生ごみには蚊やハエ、ゴキブリ、ネズミが寄ってきます。
地震で道路が被害にあうと、清掃車が走れないため、ゴミの回収はきません。
〇対策
冷蔵庫、冷凍庫の食材を調理して、消費しましょう。
食べることは出すこと。食事の前にトイレの準備を。
便器にゴミ袋をガムテープで固定し、2枚めのゴミ袋を重ねて、汚物処理剤を入れる。用を足したら2枚目のゴミ袋の口を絞めてゴミの回収が始まるまで、保管しましょう。
可燃ごみ(生ごみ含む)も汚物も各家庭で保管しましょう。
|