拡大定例会第8弾「小児性愛という病・・・それは、愛ではない」ご報告
公開日:2020年01月13日 最終更新日:2022年11月18日
| タイトル | 拡大定例会第8弾「小児性愛という病・・・それは、愛ではない」ご報告 |
|---|
詳細
 参加者の皆さまにご記入いただいた感想をご報告いたします。 |
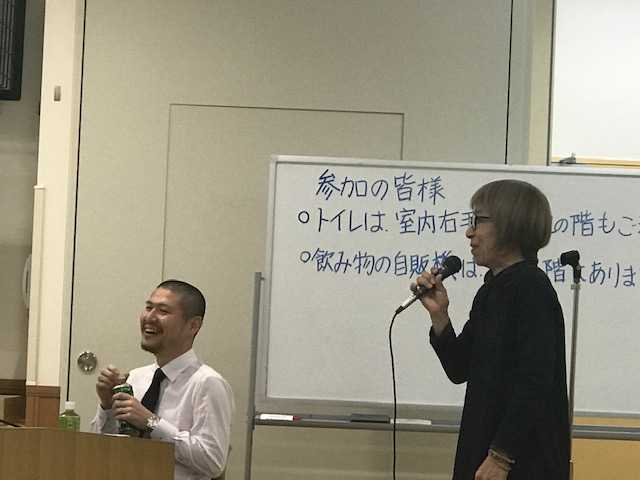 |
 |
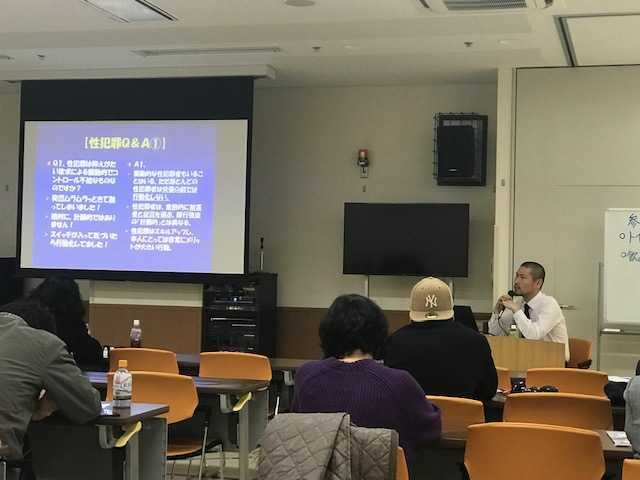 |
公開日:2020年01月13日 最終更新日:2022年11月18日
| タイトル | 拡大定例会第8弾「小児性愛という病・・・それは、愛ではない」ご報告 |
|---|
 参加者の皆さまにご記入いただいた感想をご報告いたします。 |
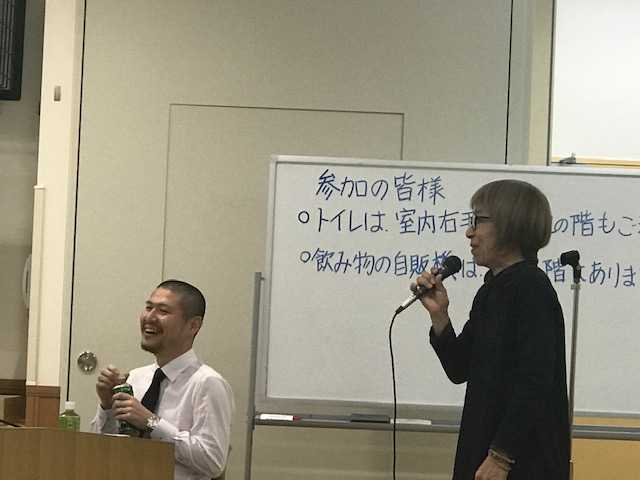 |
 |
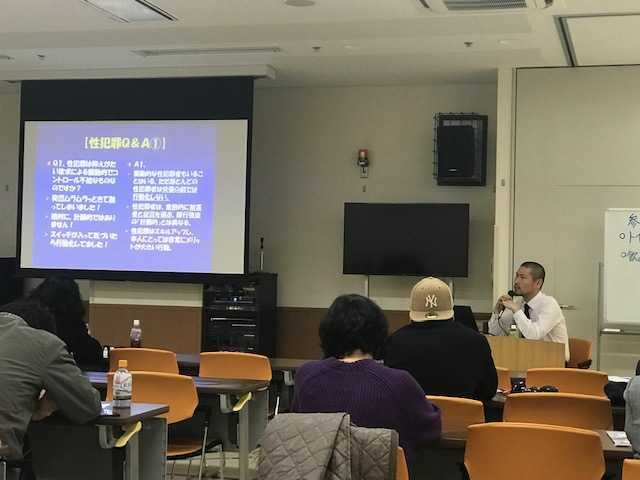 |